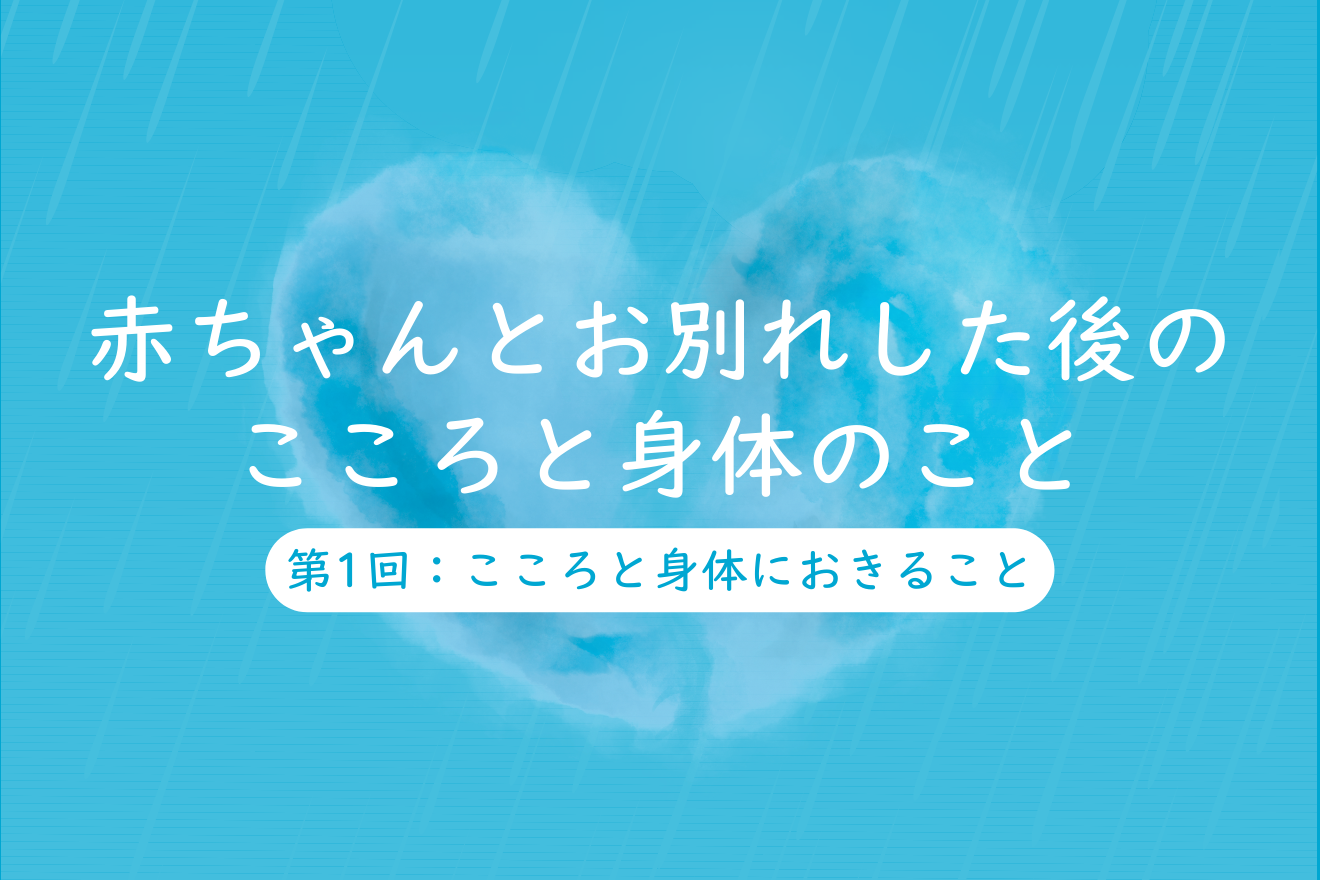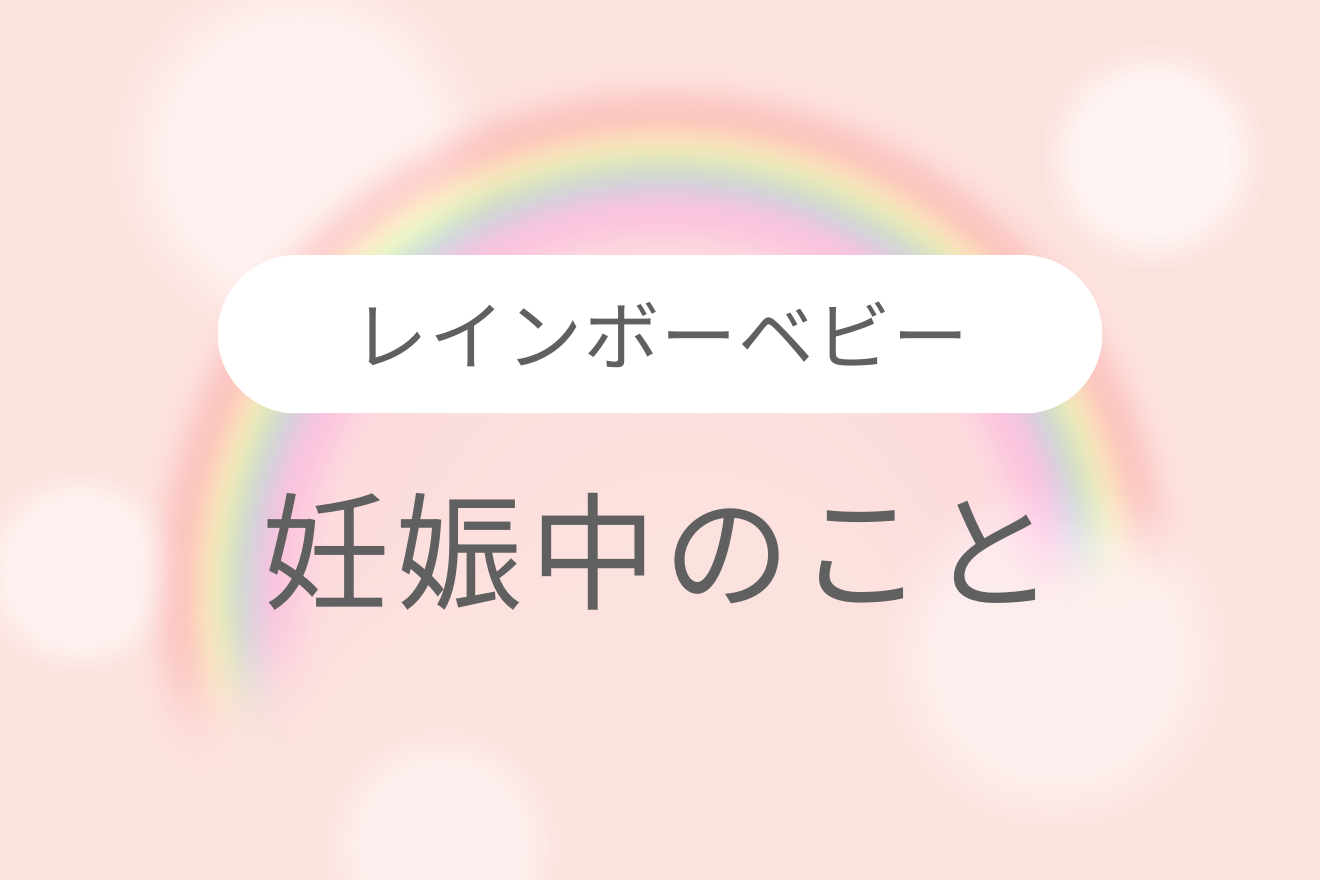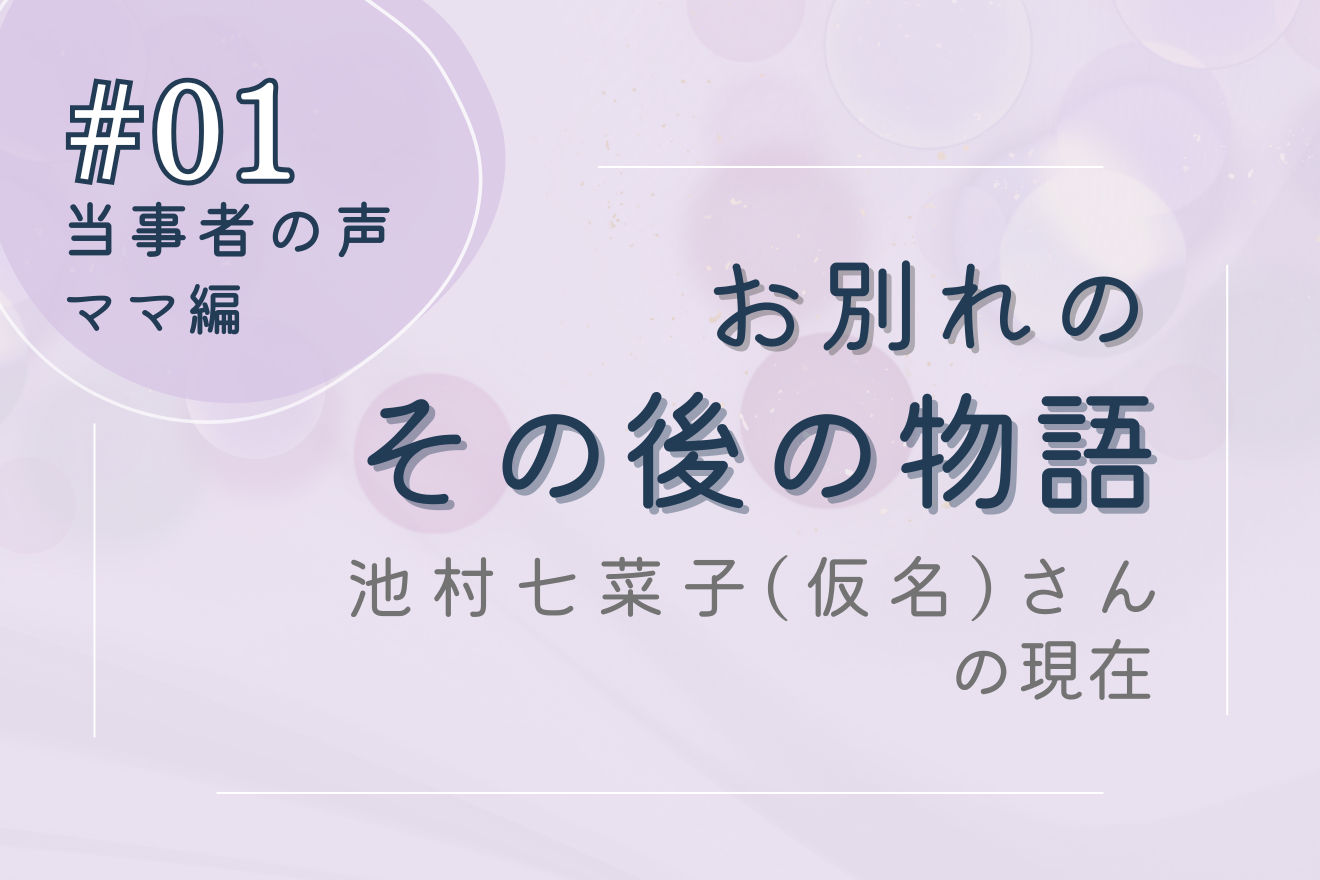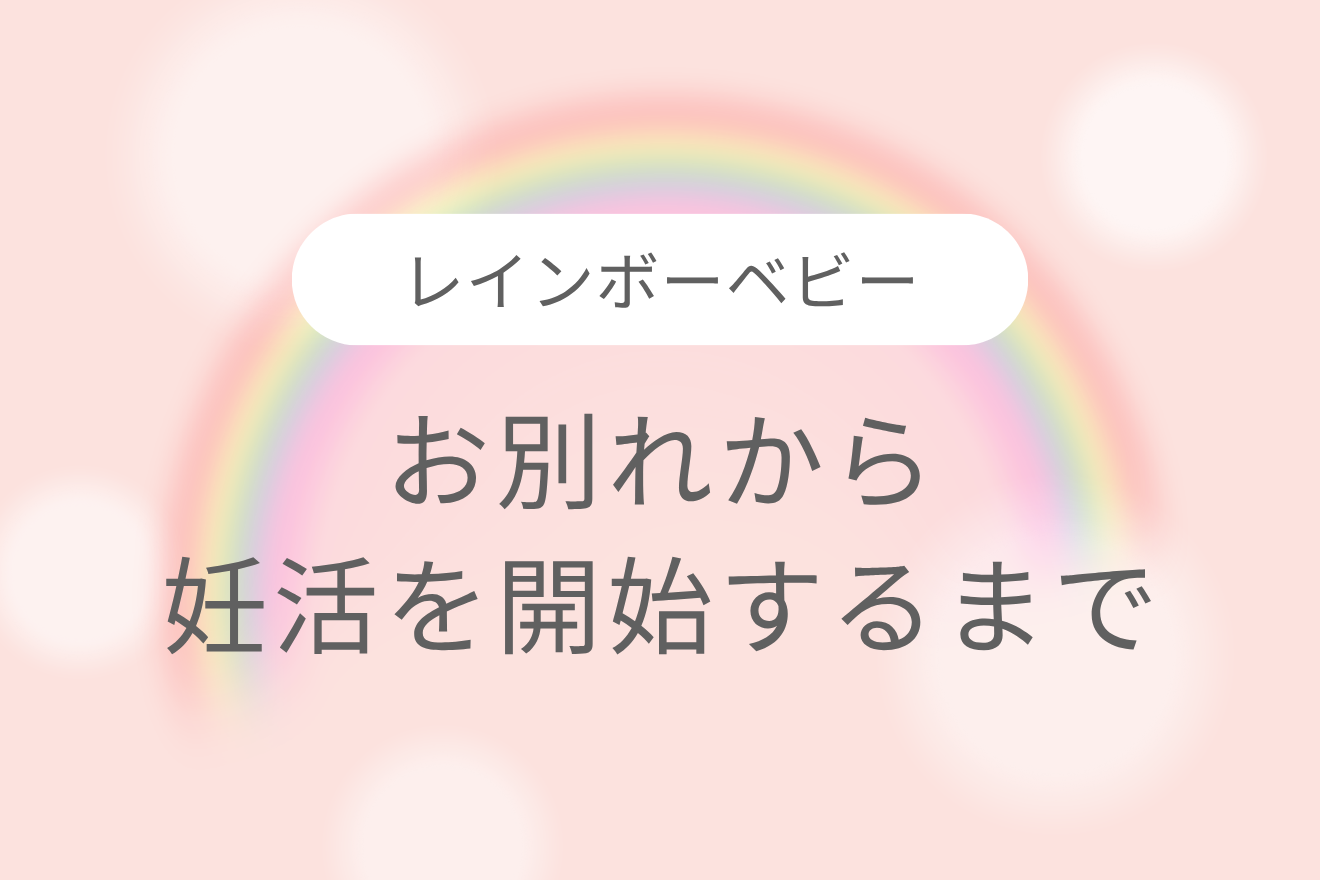「赤ちゃんとお別れした後のこころと身体のこと」は、全4回のコラムです。
流産・死産・新生児死等を経験された方や、そばにいる方に向けて、こころと身体のこと、気持ちとの付き合い方、大切にしたいケアについてお届けします。
私たちSORATOMOは、赤ちゃんとのお別れのあとにも、日々を生きていく力を誰もが持っていると信じています。このコラムが、そんな力を思い出すきっかけや、そっと寄り添う言葉のひとつになれたらと思います。
第1回では、赤ちゃんとお別れした直後に起こるこころと身体の変化についてお話しします。
第1回 こころと身体におきること
赤ちゃんとお別れした後、私たちには様々なこころと身体の変化が起きます。
こんな状態だけど、私はおかしいのかな?
私だけなのかな?
人格が変わっちゃったのかな?
そう不安に思うママ達にたくさんお会いしてきました。
結論からいうと、大丈夫です。あなただけではありません。おかしくもありません。あなたの根幹である人格が変わったわけでもありません。
どんな変化も、大切な我が子とお別れした後、その時に起こりうる自然なこころや身体の反応の一つです。
必ず起こる身体の変化
こころや身体に起こる変化は、出産の影響によるものとお別れの経験の影響によるものが絡み合っています。
まず、赤ちゃんとお別れした後のことを考える時に忘れてはならないのは、身体の変化です。
赤ちゃんとのお別れにはさまざまな背景があり、また時期も様々です。ご自身で身体の変化を感じにくい方も多くいらっしゃると思います。
もちろんお別れの週数や出産の方法によって程度に差はありますが、お別れの後、身体は物理的に傷つく場合が多く、ホルモンバランスの変化はに至っては誰にでも必ず訪れます。
出産に伴う物理的な変化・ダメージ
赤ちゃんを育てる準備をしていたママの身体、その流れが急に止まることでの負担はもちろん、出産により物理的に傷つく場合があります。
早期流産はそれ自体による物理的なダメージはほとんどないと考えられますが、措置や経過によっては傷つく場合もあります。
経腟分娩では、骨盤底筋群(骨盤まわりや内臓を支える筋肉)や肛門括約筋(排泄に関わる筋肉)などが損傷を受けたり、機能が低下したりする可能性があります。また、会陰の損傷や恥骨へのダメージが生じることもあります。
帝王切開の場合には、お腹だけでなく子宮も切る手術であり、それ自体が大きなからだの負担になります。
ホルモンの大きな変動
物理的なダメージに加えて、赤ちゃんをお腹の中で育てていたママ達の身体には、出産の前後でホルモンバランスの変化も訪れます。お別れの週数によってその変動の大きさに差はありますが、早期流産~死産、新生児死まで、どの時期のお別れであっても必ず起こります。
この変化により身体に変調があったり、痛みを伴う場合も少なくありません。
出産前の身体に戻るには、当然個人差がありますが、正期産に近い週数での分娩では最低でも約6週間~8週間かかるとされています。
ホルモンバランスの変化は、身体だけでなくもちろんこころへも影響します。身体がもとに戻るまでの時期は、自律神経や気分に影響を与え、精神的に不安定になりやすい時期だということも分かってきています。
出産による物理的なダメージはしっかりと休み、回復するのを待つしかなく、コントロールできるものではありません。同様に、ホルモンバランスの変化の影響によるこころの変化も「気の持ちよう」などでコントロールすることはできません。
出産後は、お別れの後ということだけでなく、身体もこころも不安定で当然な時期なのです。
こころに起こること
出産に伴う心身の変化だけでなく、お別れを経験したことによるこころの変化も、たくさんあります。
お別れの後、さまざまな変化を感じている方が多いのではないでしょうか。
気持ちが揺れ、時に沈み、身体の感覚が変わったり……。
先にお伝えした出産後の心身の変化の影響もありますが、お別れの後の様々なこころの反応があります。それらを「悲嘆(グリーフ)」といい、赤ちゃんとのお別れだけでなく、大切な人とのお別れの後、多くの方に共通して見られることがわかっています。
悲嘆(グリーフ)は「身体的反応」「情動的反応」「認知的反応」「行動的反応」の4つに分類できます。図-1はSORATOMOが赤ちゃんとのお別れの後に特に見られると考えた反応を、分類ごとにまとめています。
図-1
これらの反応全部を全ての人が経験するわけではありませんが、どの反応も、またここには書ききれない他の反応も、大事な人を亡くした時に出てくる自然な反応です。
弱いわけでも、気持ちの切り替えができないわけでもありません。
人格が変わってしまったのかも?と思われがちな「怒りっぽくなった」「赤ちゃん連れを見てるとイライラする」「心が狭くなった」なども、悲嘆(グリーフ)のひとつと考えられます。
悲嘆(グリーフ)は行きつ戻りつしながら自然に軽快していくことがほとんどですが、お別れを経験したあとの今、こころや身体が辛い状況にあって当然です。
そして、お別れから時間が経っていても、何かのきっかけでまたこころの反応が出てくることも十分ありえます。長い時間が経ったからといって、こころに悲しみがあり続けることもまた、おかしなことではありません。
コントロールできないこころの反応
悲嘆も、ホルモンの変化も、自分の意思ではどうすることもできません。コントロールすることも意識的に切り替えることもできません。
まずは、上記のようなこころの反応が起こりうることを知っていただければと思います。
ご自身の中で起こっている変化や感じていること、できないこと、涙がでること、どれも自然な反応です。
まずは身体を休ませることを優先しつつ、たくさん泣いたり、赤ちゃんを愛しく思ったり、寂しいと思うことも、そのこころの動きはおかしくないよ、当然だよ、とご自身を抱き締めてあげてください。
回復までの道のり
では、私たちのこころはどのように回復していくのでしょうか?
今まさに辛いなかにいると、いつまでも続くような気さえしてくるかもしれませんが、見通しがあると少し安心かもしれません。
身体の物理的なダメージやホルモンバランスの変化は時間とともに回復していきます。
悲嘆についても、人それぞれのプロセスをたどりながら日常生活へと次第に適応できるようになっていくと言われています。
次回のコラムでは、回復までの道のりについて、そもそも「回復」という言葉が適切なのかということも含めて、ご紹介していきたいと思います。
最後に
こころの変化は自然な反応であるとお伝えしてきましたが、無理に元気になろうとしたり、今ある身体やこころの反応を「気のせい」として無視したり、蓋をしてしまったり、またはお別れの経験が大きすぎて圧倒されてしまうと、自力では回復できないということも起こりえます。
日常生活を送ることが困難になるほどの激しい反応やフラッシュバックがあったり、長期間全く変わらないレベルで悲嘆が続いたりする場合などは、医療機関への受診をご検討いただきたいと思います。
また、一人で抱え込みすぎないというのも大事です。誰かと話したい、赤ちゃんの話がしたい、そう思うのも当然です。
無理に話す必要はありませんが、話したいなと思えるタイミングがきたら、ご家族やご友人など、信頼できる方とお気持ちをシェアしてください。
もし誰にも話せない時は、様々な団体が同じ経験をされた方のおしゃべり会を開催しているので、そのような会への参加もいいかもしれません。
SORATOMOでも月に1回おしゃべり会を開催したり、専門家によるオンラインカウンセリングサービスも開始しております。私も臨床心理士として相談をお受けしておりますので、そちらもご検討いただけたら幸いです。
SORATOMOおしゃべり会のお知らせはこちら
著者(取材・文=SORATOMOライター まちゃ(臨床心理士・公認心理師))
<参考文献>
永田雅子|『周産期のこころのケア』|2022年
瀬藤乃理子、広瀬寛子|『グリーフケアとグリーフカウンセリング』|2023年
J.W.Worden|『悲嘆カウンセリング[改訂版]』| 2023年
この記事はSORATOMO編集部が独自に調査し、編集したものです
記事の内容は2025年5月の情報で、現在と異なる場合があります